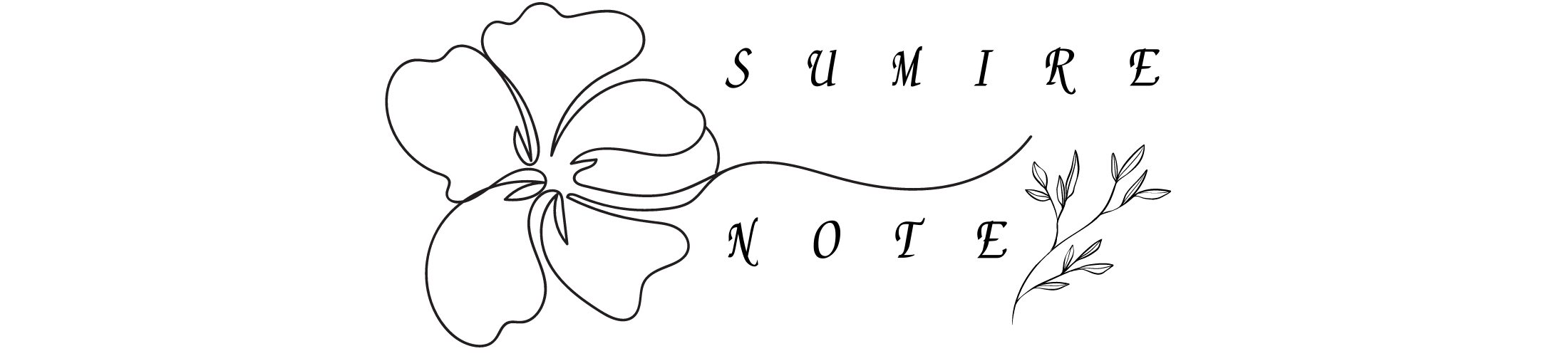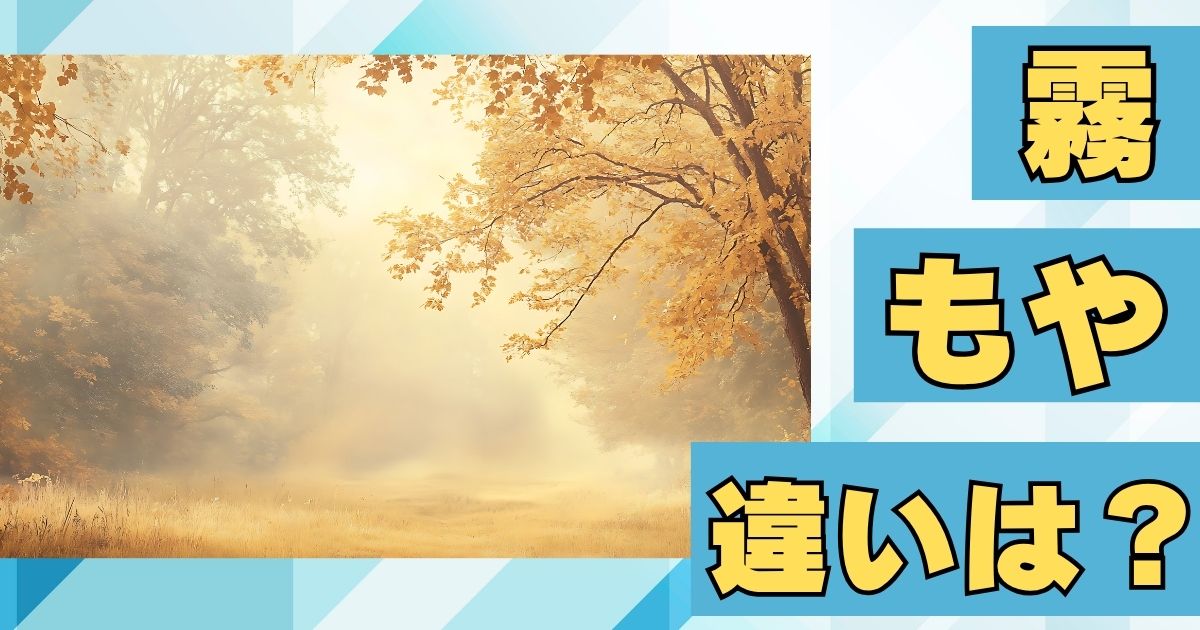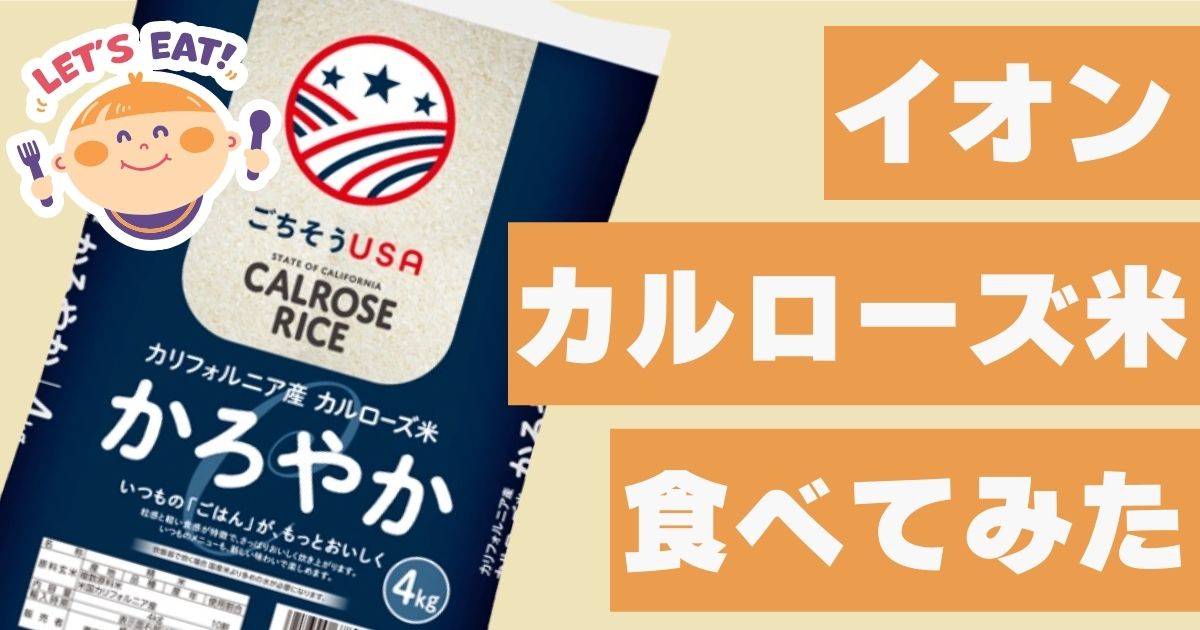こんにちは、すみれです!
栃木県埋蔵文化財センターの夏の企画展に行ってきました。
今回ご紹介するのは、文化財センターで出会った顔から国宝まで、私のお気に入りの土偶です。
縄文時代に作られているにも関わらず、現在にまで魅力を放ち続ける作品たちです。
たくさんの顔!
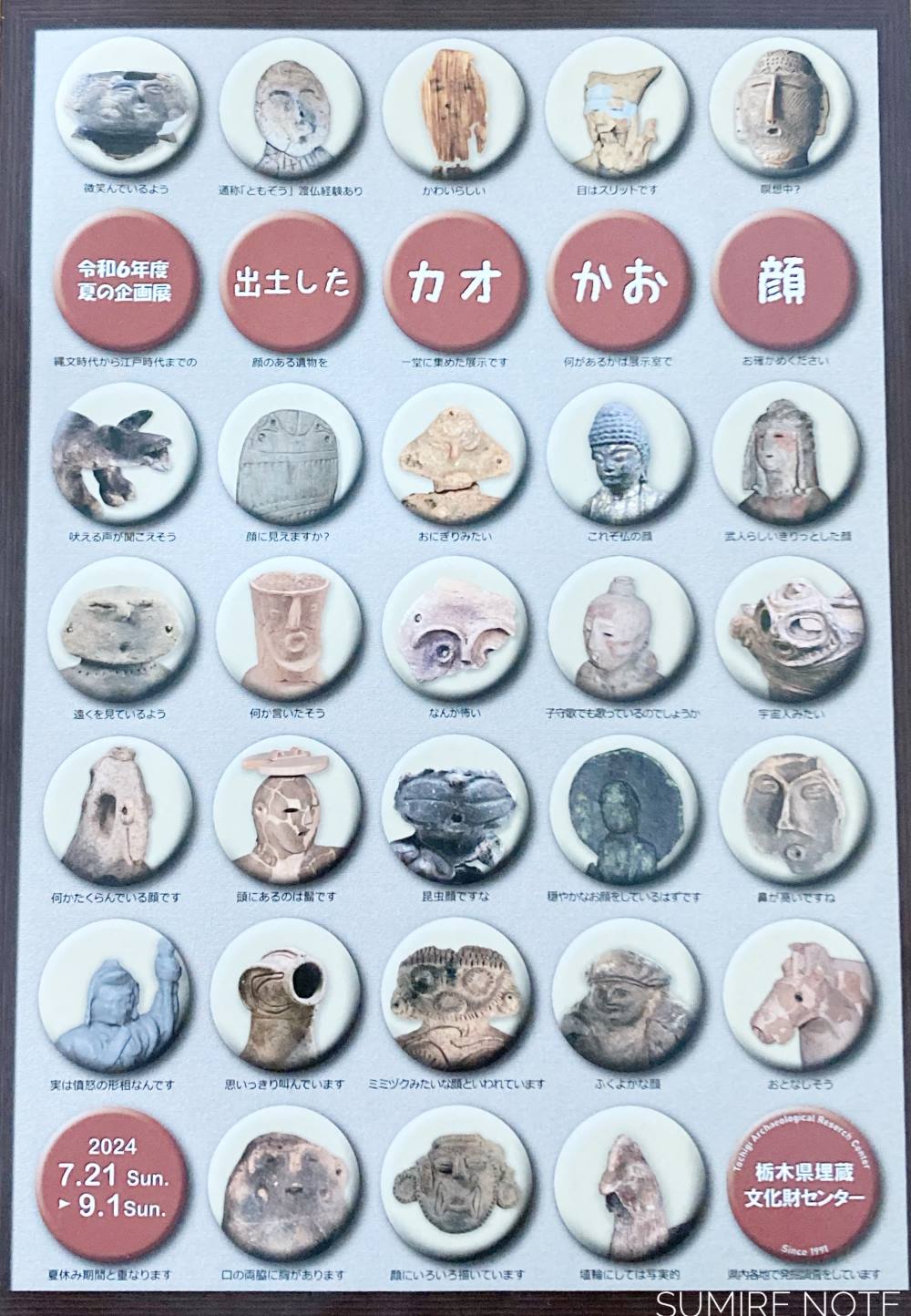
栃木県埋蔵文化財センターでは、「出土したカオ・かお・顔」というテーマで、夏の企画展が開催していました。
遺跡から出土した遺物の中から、顔の表情が見られるものを集めた企画展です。
すみれのお気に入り「顔」ベスト3!
埋蔵文化財センターの企画展では、個性的な顔と出会えました。
私が気に入った顔を紹介したいと思います。
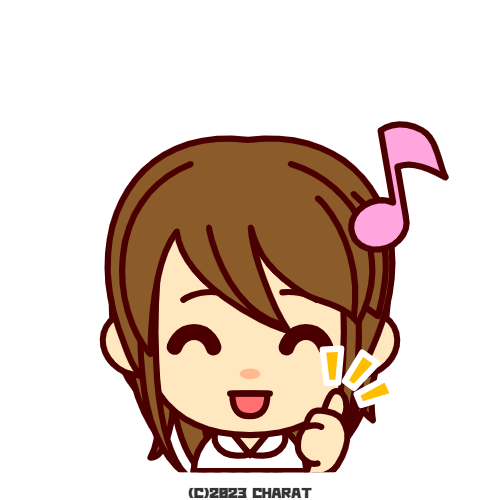 すみれさん
すみれさん埋蔵文化財センターの方に許可を頂いて、顔を撮影してきました!
第3位 人面付注口土器


こちらの土器は、縄文時代晩期に作られたものです。
土器に顔が付いているものです。
器に顔が付いていると思うと、ちょっと怖い気がします。
しかし、描かれている顔がとても穏やかです。



仏様のような顔で、癒されます。
第2位 ハート形土偶


展示されていたハート形土偶は、鼻がくっきりしていて、腰から下にかけて描かれている模様がステキでした。
ハート形土偶とは?
顔の形がハートの形をしている土偶のこと。
縄文時代の後期に作られ、主に関東から東北南部で出土しています。
群馬県の郷原遺跡から出土したハート形土偶は、高さ30.5㎝あり、国指定重要文化財に指定されています。
群馬県東吾妻町の交差点には、巨大なハート形土偶が設置されています。
第1位 人面付土版


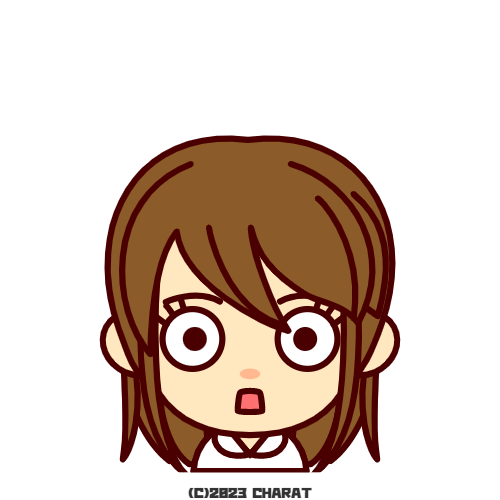
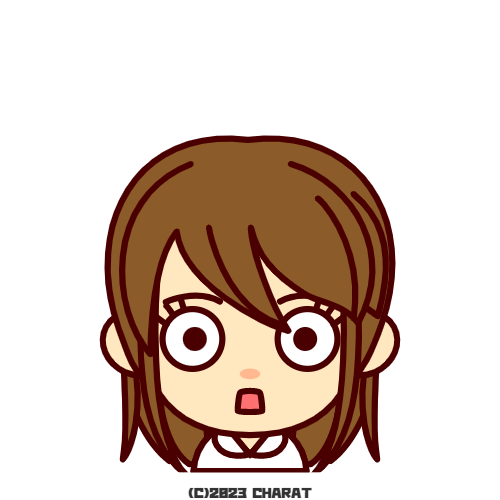
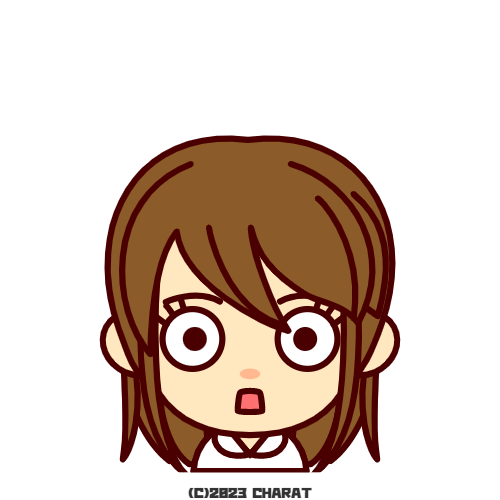
見てください!この気が抜けた感じ!!
ゆるキャラを思わせる表情が、なんとも言えません。
縄文時代晩期に作られた土板です。
土版とは?
土版は、岩版ともに、呪術用やお守りとして使用されました。
縄文時代の末期、東北地方や関東地方を中心に出土しています。
土版は粘土、岩版は凝灰(ぎょうかい)岩や砂岩などの柔らかい石で作られています。
土偶と埴輪の違って?
土偶と埴輪の違いは、作られた時代や目的が異なります。
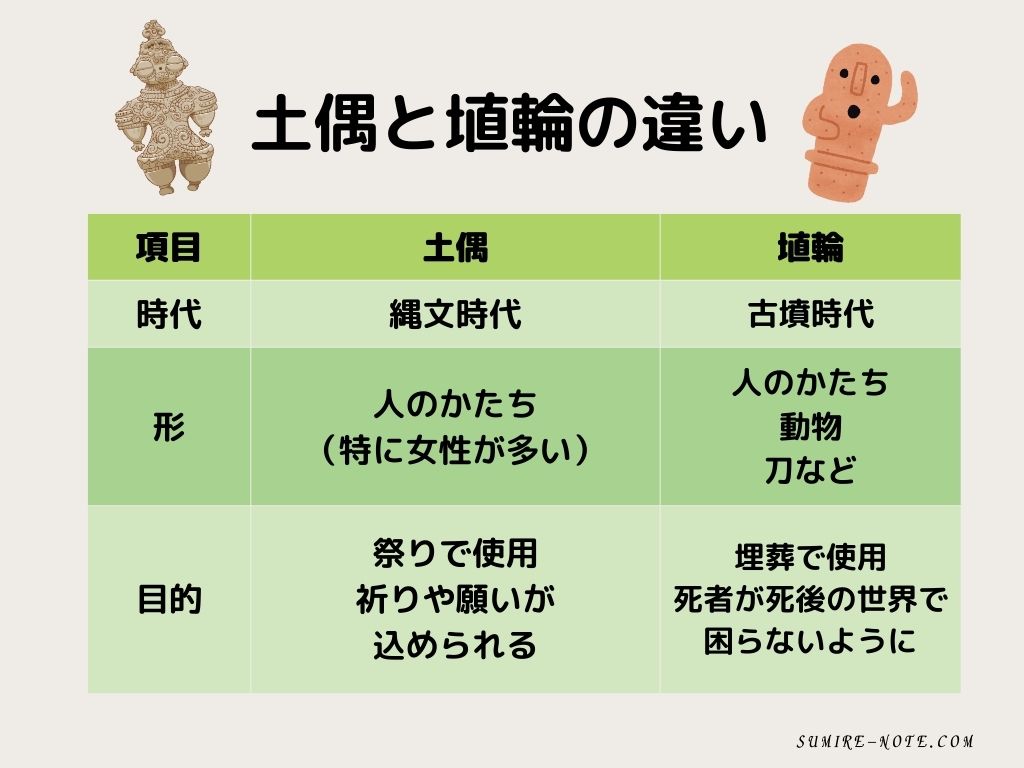
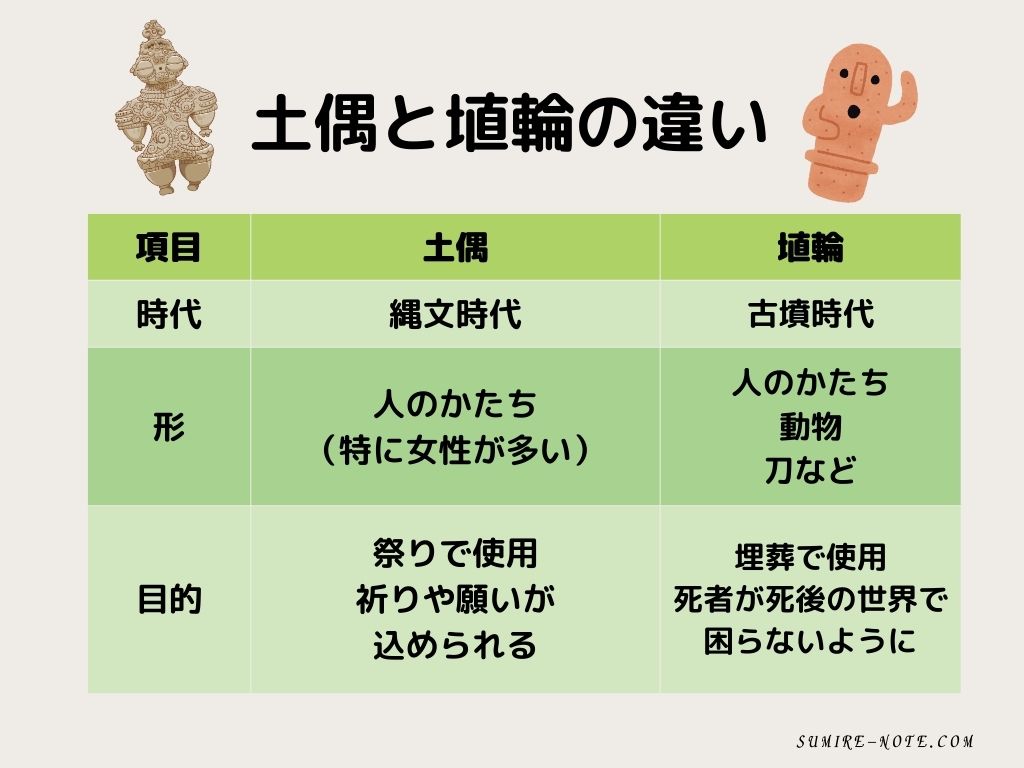
まず、土偶は縄文時代に作られています。
土でできており、人の形をしています。
多くは女性を型取り、乳房があり、お腹の膨らみを表現しています。
土偶は、子孫繁栄や五穀豊穰を願って作られました。
また、身代わりや魔除けの役割を担うこともあり、あえて体の一部が壊されます。
そのため、土偶は手足がない状態で見つかることが多いのです。


一方で、埴輪は古墳時代に作られます。
素焼きで、人の形以外にも、動物や刀、家具などの形があります。
亡くなった人が、死後の世界でも困らないように、古墳の周りに埴輪を置いたとされています。
国宝になっている土偶とは?
土偶の中でも、国宝に指定されているものは、これから紹介する5点のみです。(2024年9月時点)
いつか実物を見てみたいと思う、とても魅力的な土偶です。
縄文のビーナス(1995年国宝指定)
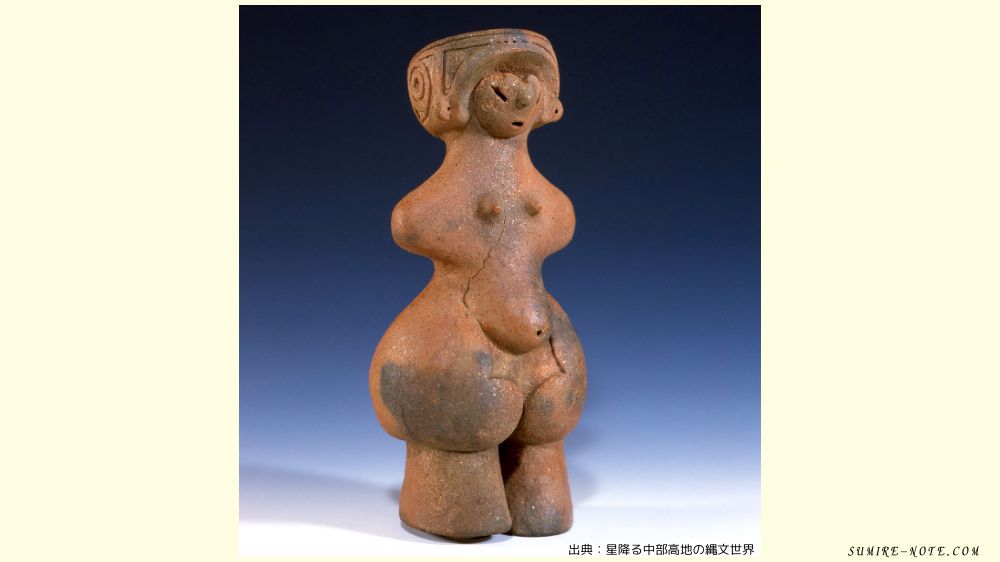
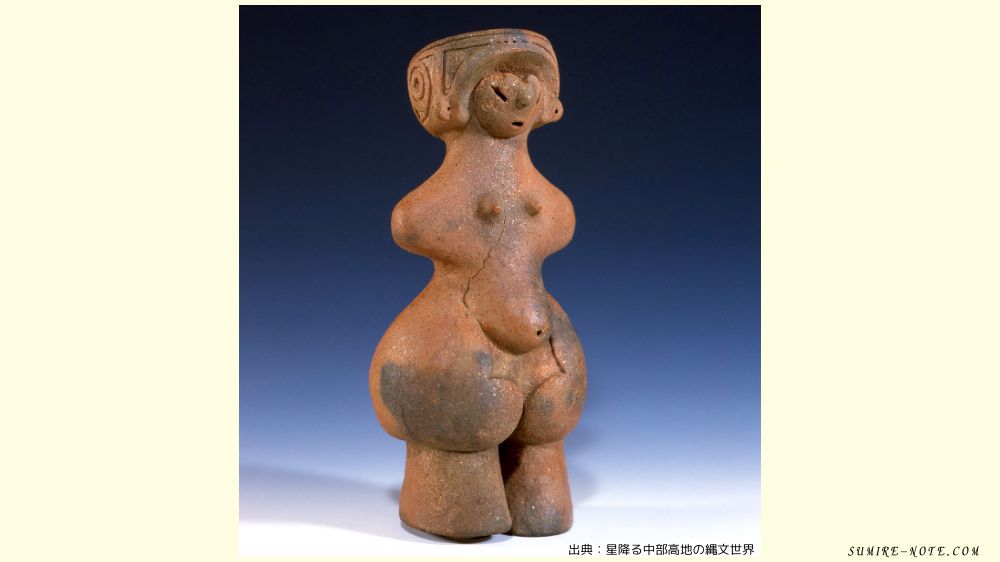
縄文時代の出土において、初めて国宝に指定された土偶です。
お腹と下半身が強調されており、独特なフォルムをしています。
縄文時代は、住宅が集まる中心に広場が設置されます。
縄文のビーナスは、広場の中心部から出土しました。
多くの土偶がバラバラに壊されますが、縄文のビーナスは、横に安置されており、壊される様子が全くありませんでした。
中空土偶(2007年国宝指定)


北海道函館市南茅部地区の著保内野(ちょぼないの)遺跡で出土された土偶です。
南茅部の「茅(カヤ)」と中空土偶の「空(くう)」をくっつけて、「(茅空)カックウ」という愛称で呼ばれます。
中が空洞な土偶である中空土偶の中で、最も大きく、高さ41.5㎝です。
顔立ちがはっきりしており、大きな肩とくびれた胴体が特徴的です。
合掌土偶(2009年国宝指定)
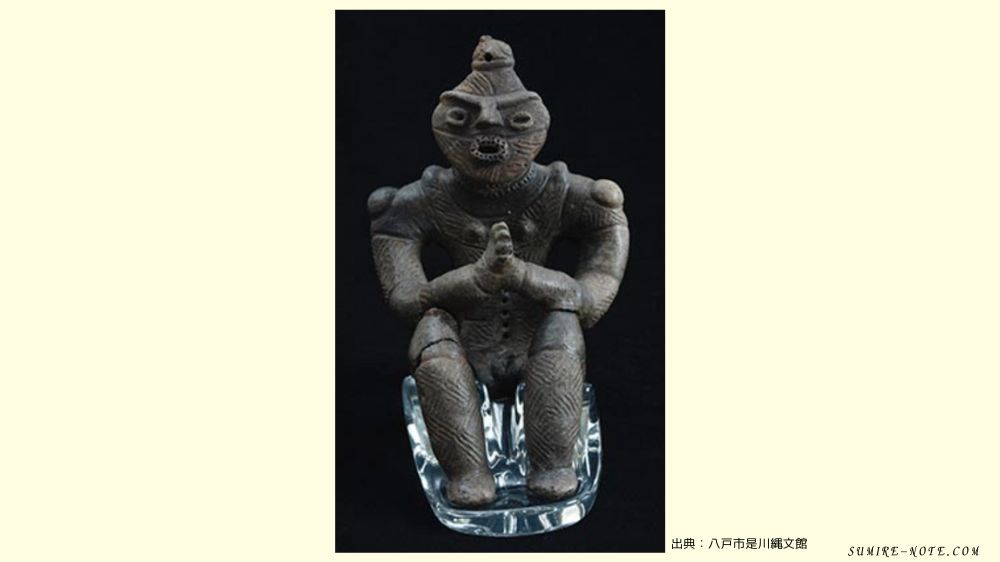
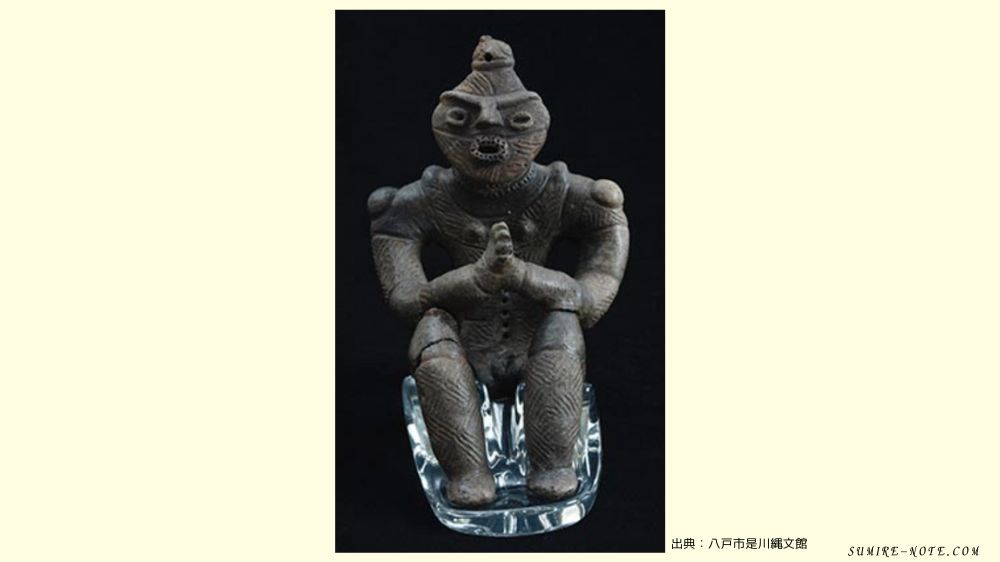
青森県八戸市の風張(かざはり)遺跡において、堅穴住居跡の壁に寄りかかるように出土しました。
座った状態で両腕を膝の上に置いて、両手で指を組んで合掌する姿から「合掌土偶」と呼ばれています。
体育座りをしている土偶は、全国でも珍しいです。
合掌土偶は、4つに割られましたが、天然のアスファルトで補修されており、大切に扱われていたと推測されます。
縄文の女神(2012年国宝指定)
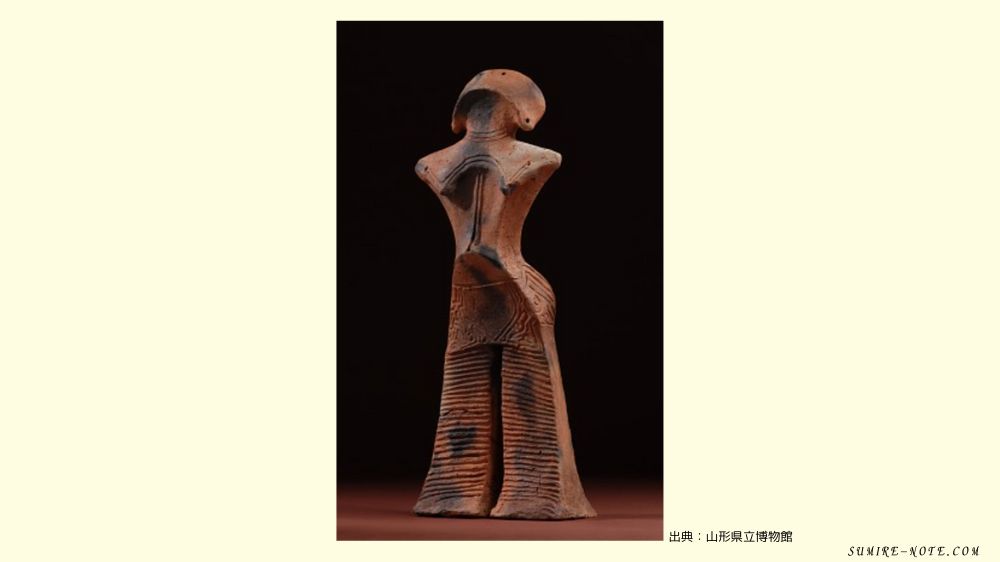
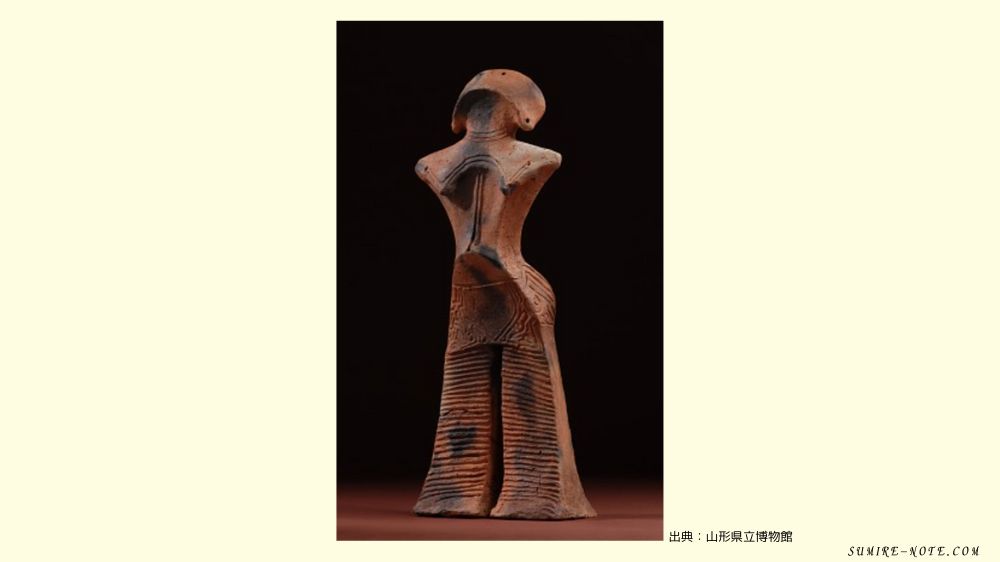
形が残っている土偶の中でも、日本で最大の土偶になり、高さが45㎝あります。
山形県舟形町にある西ノ前遺跡から出土しました。
顔は上を仰ぐようで、表情はシンプルです。
腕がなく、上半身は横から見ると薄くスリム。
お尻は出っ張っていて、パンタロンを履いているように、足は裾広がりです。
均衡がとれて美しいところから、縄文の女神と呼ばれるようになった土偶です。
仮面の女神(2024年国宝指定)
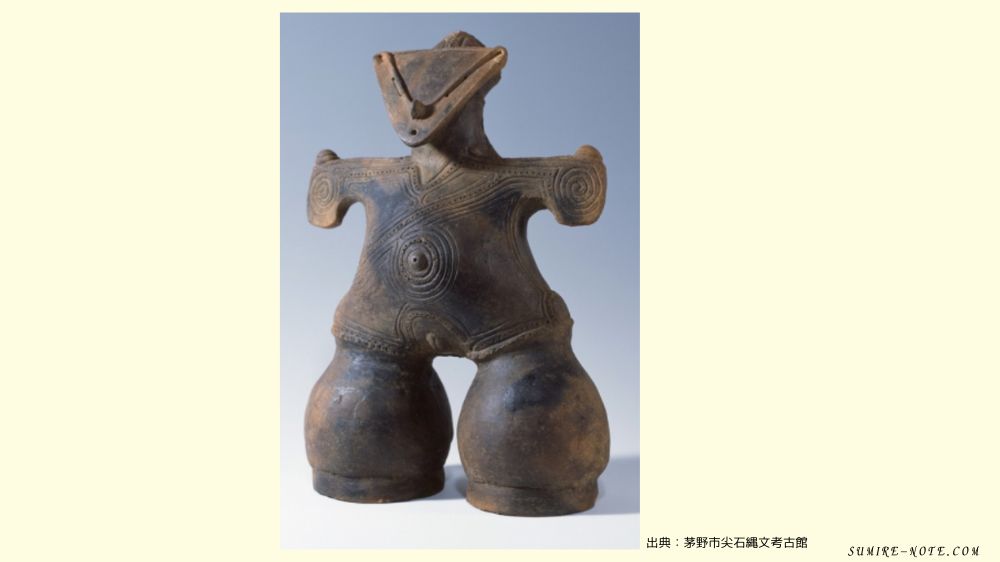
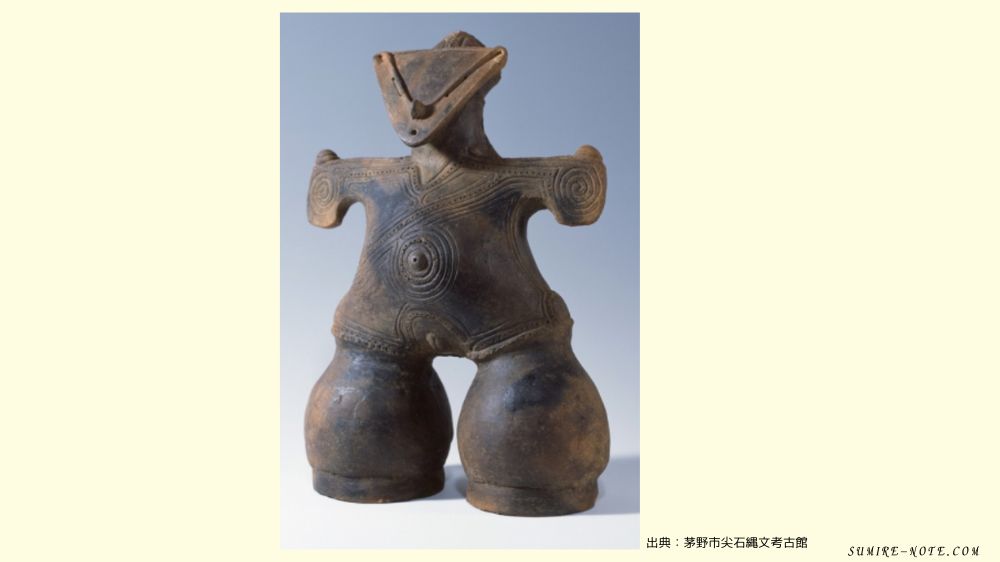
長野県茅野市湖東(こひがし)の中ッ原遺跡から出土した大形土偶です。
高さ34㎝、重さ2.7㎏で、全身がほぼ残った状態で見つかりました。
逆三角形の仮面をつけたような姿から、仮面土偶と呼ばれる土偶です。
仮面の女神は、右足が胴体から離れた状態で出土しましたが、人為的に行われた可能性が高いそうです。
仮面の女神が埋められた目的は、はっきり分かっていません。
まとめ
- 遺跡から出土した遺品の顔に注目すると、推しの顔に出会える
- 土偶と埴輪の違いは、時代や目的が異なる
- 国宝に指定されている土偶は5点のみ(2024年9月時点)
土偶をながめていると、私たちの祖先の様子や思いを想像します。
美術品としても高く評価される土偶は、現代にも通用する美しさがあると思います。
生きている間に、国宝の土偶を実物で見たいものです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。