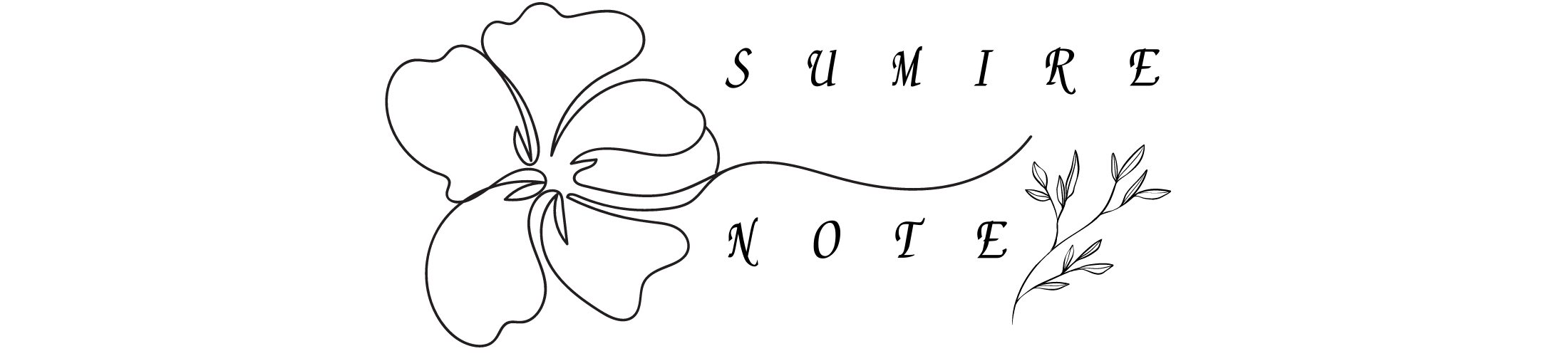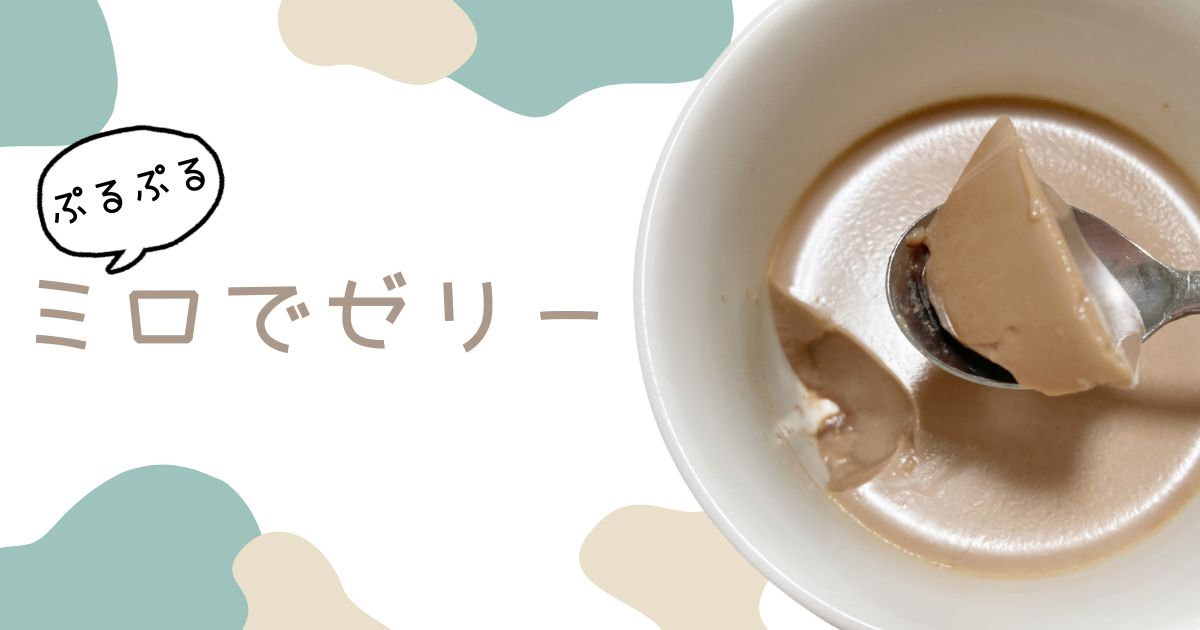こんにちは、すみれです!
みなさん、ゴールデンウイークは楽しみましたか?
ゴールデンウイークは祝日が続いていますが、「こどもの日=端午の節句」と思っている方も多いのではないでしょうか?
今回は「こどもの日が5月5日になった理由」について、ご紹介したいと思います。
こどもの日が5月5日になったのは、どうして?

こどもの日が5月5日になったのは、予定していた日が、先に憲法記念日になってしまったからです。
戦後の1948年、国会では、すべての祝日を見直す会議が行われていました。
5月3日から5月7日は、雨が少なく天候が良い日が多いことから、こどもの日の候補日になります。
さらに、端午の節句の5月5日と、桃の節句の3月3日から、5月3日をこどもの日にする案が出ていました。
しかし、こどもの日より先に、5月3日が憲法記念日となり、5月3日をこどもの日にする案は却下。
もともと端午の節句であった5月5日が、こどもの日となり、祝日になりました。
こどもの日「5月3日案」もあった 端午の節句だけ、なぜ祝日に?
こどもの日には、母に感謝する目的があった

こどもの日は、下記の目的があります。
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福を図るとともに、母に感謝する
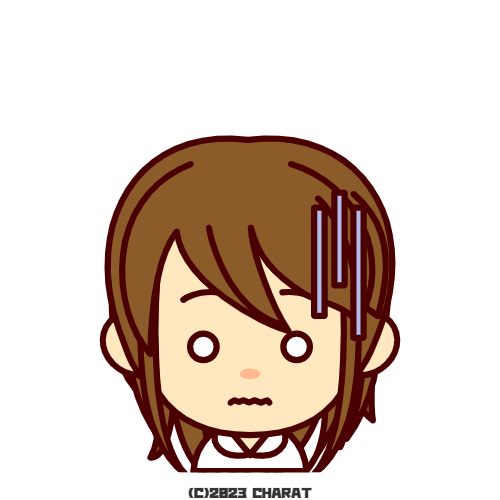 すみれさん
すみれさんこどもの日に「母に感謝する」目的があるとは知りませんでした。
こどもの日は、国民の祝日に関する法律によって、定められています。
母に感謝する日として、日本では5月第2日曜日が「母の日」が主流になっています。
こどもの日=端午の節句ではない


先ほども述べましたが、こどもの日ができる前に、日本の風習として「端午の節句」がありました。
つまり、こどもの日と端午の節句は、同じではないのです。
こどもの日は、男女問わず、子どもの成長を願う祝日です。
一方で、端午の節句は、男の子の成長を願う伝統行事です。
端午の節句に行う風習
端午の節句では、さまざまな形で男の子の健やかな成長を願います。
鯉のぼりを飾る


鯉のぼりを飾るのは、困難を乗り越えて立派に成長することを願うためです。
中国の古事で、流れの速い滝を鯉が登り切ると、龍になって天を昇ったという話があります。
「子どもの成長と立身出世を願う」意味を持ちます。
兜を飾る


武家の習慣で、梅雨の前に兜などの武具を干して、手入れをしていたが始まりです。
兜は武士にとって大切な装備の一つ。
子どもを守って欲しいという親心が込められています。
菖蒲湯に入る
菖蒲(しょうぶ)は邪気を払う薬草です。
菖蒲湯に入るのは、魔除けの意味があります。
柏餅を食べる


柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちません。
このことから、家系が絶えず、子孫繁栄を象徴します。
ちなみに、関東では柏餅、関西ではちまきが主流です。
まとめ
- こどもの日が5月5日になったのは、先に憲法記念日が決まったため
- こどもの日は祝日で、こどもの人格を重んじ、こどもの幸福を図るとともに、母に感謝する日
- 端午の節句は、日本の年中行事で、男の子の成長を願う日
5月3日がこどもの日になる予定がでしたが、5月3日を憲法記念日にすることが先に決まってしまい、こどもの日は5月5日になりました。
端午の節句は、日本の年中行事として国民に浸透しており、男の子の成長を願います。
一方で、こどもの日は「すべてのこどもに幸せを」という目的があり、国民の祝日です。
いずれにしても、子どもたちの健やかな成長を願いたいものです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。